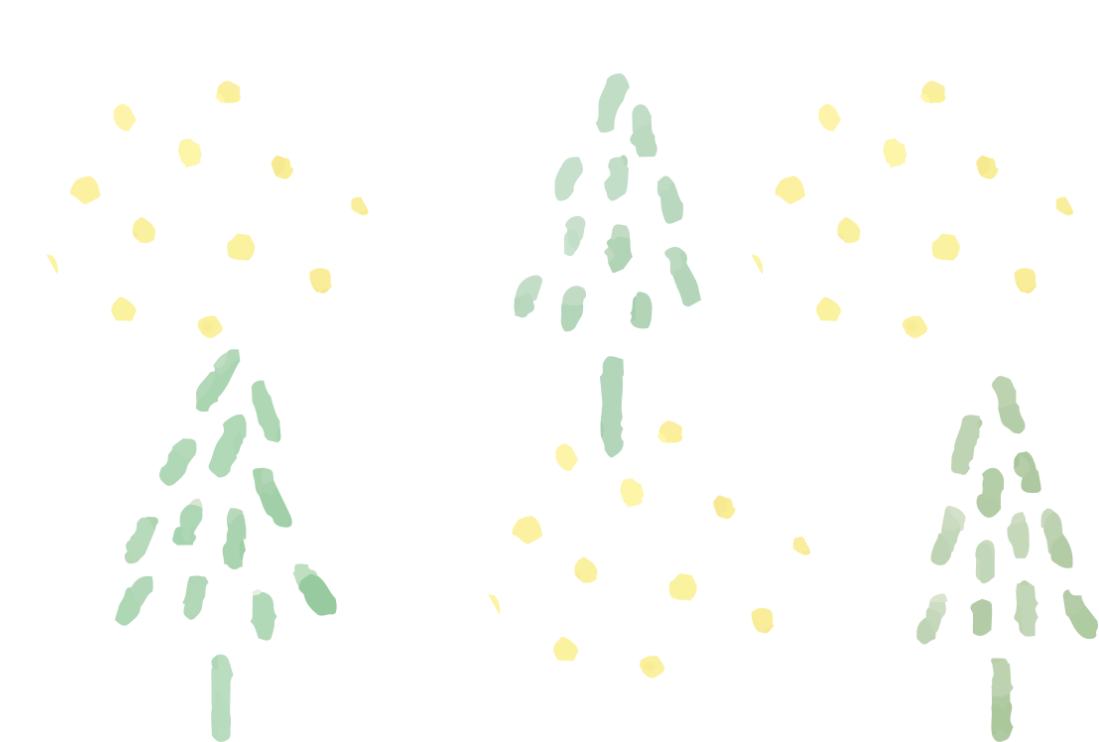春を立てる

今年は立春を過ぎてから、強力な寒波がやってきました。ただ、暦の上での「春」と気温や天候とは、そもそも、ずれがあるものではあるのかもしれません。
立春とは、紀元前の中国で生まれた暦である二十四節気において、一番最初の節気であり、新しい年のスタートや春の始まりの日とされています。現代の日本では、国立天文台の観測によって「太陽黄経が315度になった瞬間が属する日」を立春としているのだそうです。
古代の中国では、季節や星の巡りは王が支配し、王の宣言によって国民に知らされるものだったのだそうで、そのため、王が「春を立てる」という思想に基づき、「立春」となったといわれています。
一方、日本の古典文学の中では、「立春」のニュアンスも少し違っているようです。。
「ひさかたの 天の香具山 この夕べ 霞たなびく 春立つらしも」(柿本人麻呂・万葉集より)
「春立てる霞の空に、白川の関越えんと、そぞろ神の物につきて心を狂はせ、道祖神の招きにあひて取るもの手につかず、…」(松尾芭蕉・奥の細道序文より)
これらの表現を読むと、春は特定の誰かが立てるものではなく、空にたなびく霞のように、自然と、いつのまにか立っているものであるように感じられ、現代の私たちの感覚にも近いように思われます。
ところで、立春の前日の節分には、豆をまいて鬼を追い払う風習があり、今も日本の大切な伝統行事として、多くのご家庭でも行われていると思いますが、その原形のひとつとされるものに「追儺(ついな)」という儀式があります。
追儺とは、元々は中国の宮中で旧暦の大晦日に行われていた疫鬼や疫神を払う儀式が、日本でも採りいれられ定着していったものと考えられています。その儀式では、4つの目をもつ四角い面をつけ、右手に戈(ほこ)、左手に大きな盾(たて)を持ち、熊の毛皮を被った「方相氏(ほうそうし)」と呼ばれる存在が、疫鬼や魑魅魍魎たちを内裏の門から追い出して都の外へと払います。
方相氏は、そのつけている面やいで立ちから、見た目は恐ろしく見えますが、本来、鬼ではなく、むしろ鬼、邪気や悪霊を追い払う存在でした。元々は、追い払われる側の鬼役は登場せず、方相氏や陰陽師らが、目には見えない鬼たちを追い払うという儀式が行われていたようです。しかし、時代が下るにしたがって、鬼役が登場するようになり、平安時代以降になってくると、方相氏が鬼と同じように払われる側の存在に変化していったとみられる記録が増えていくのだそうです。追い払う側の役割だった方相氏ですが、その外見が似ていたことも影響してか、次第に、正反対の追われる側の鬼へと扱われ方が変化していったものと考えられているようです。
「立てられる」ものなのか、「立つ」ものなのか、「追い払う」ものなのか、「追い払われる」ものなのか…。正反対であるようでいて、存外、容易に反転してしまうものでもあるのかもしれません。また、それを見る立場によっても、変わってくるものでもあるのでしょう。自分は今、どちらの側から何を見ているのか…、そういった視点も忘れずにいられればと思います。