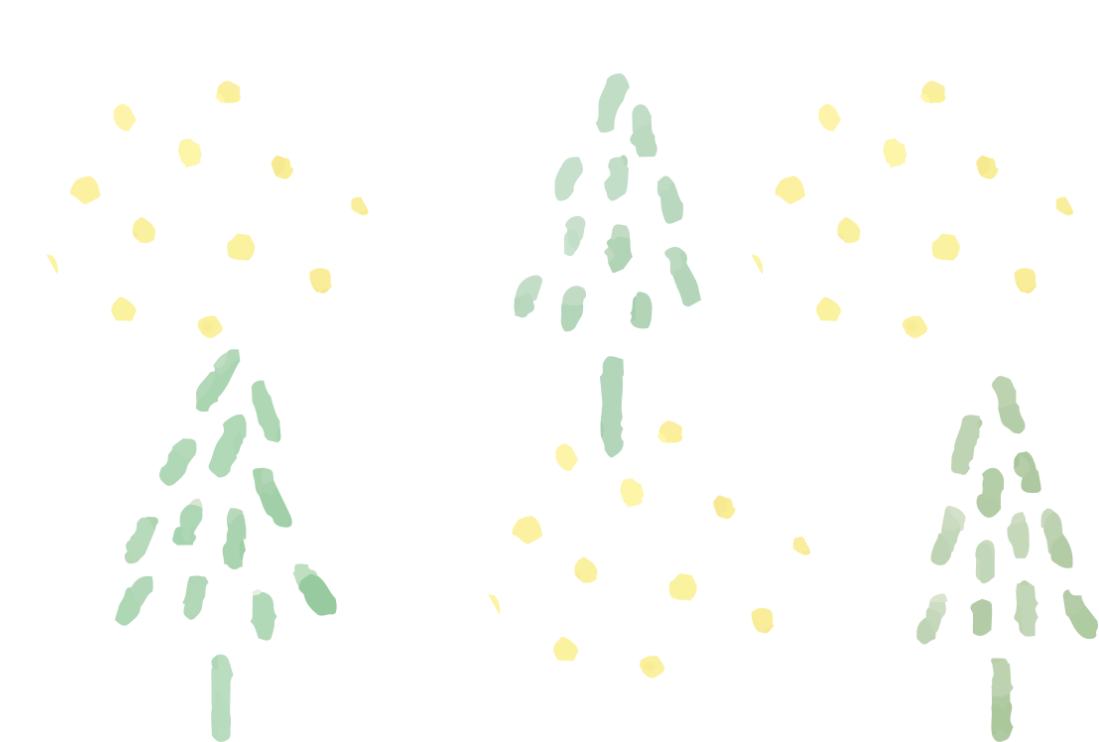あそび

FROLOGの窓から外を眺めると、集合住宅が道沿いに見える。その集合住宅は、盛土した土地に建っているので敷地が道より少し高い。
ある時、親に手をひかれて歩道を歩いてくる園児の姿が目に入ってきた。
集合住宅の前に差し掛かると園児は繋いでいた手を放して、自転車用のスロープを駆け登った。そして、敷地を2mほど歩道と平行に進むと、今度はその先にある階段を下りて歩道に戻ってきた。
何とも楽しそうで、また、ひとりでやり遂げた感を醸し出した誇らしげな表情からも、ほっこりした気持ちになった。
実はこの集合住宅の敷地内に、自動販売機がある。飲み物を買うことが目的の人は、自動販売機に一番近い階段から登って、同じ階段を下りる。それが最短ルートだから、正解になる。ただ、そこに"あそび"はない。
とかく効率優先の社会の風潮を心配に思う。
大人も子供もきちきちした"あそび"のない日常を送っているように感じるからだ。早く目的を達成するために、コスパの良さや近道こそが評価されるのだ。
"あそび"は大事。あたりまえのことかもしれないが、ときどき忘れてしまう。
今の時代の子どもたちが夢中になる"あそび"というと、デジタル技術によるゲームになるだろう。ゲームのようなバーチャルな"あそび"は、決められたルールに従って処理するための脳が使われるそうだ。
一方、けん玉、お手玉、折り紙・・・などの昔の"あそび"は、失敗を繰り返しながら成功できる状態を見つけようと脳が活性化して成長して行くと言われている。
昔の子どもたちは、遊びを通して自然にさまざまな力を身につけていった。
子どもたちが屋外で体を動かして遊んでいた頃とは、遊びの質がまったく変わってきている現代。あの頃の人間らしい体感を取り戻すには、意識的にリアルな体験を取り入れる必要があるのかもしれない。
そしてそれは、ゆとりのない日常をおくっている大人にも子どもにも、きっと必要なことだと思う。
皆さんも、昔の"あそび"を見直してみてはいかがでしょう。
私もこころに"あそび"を持ち続けたいと思っている。