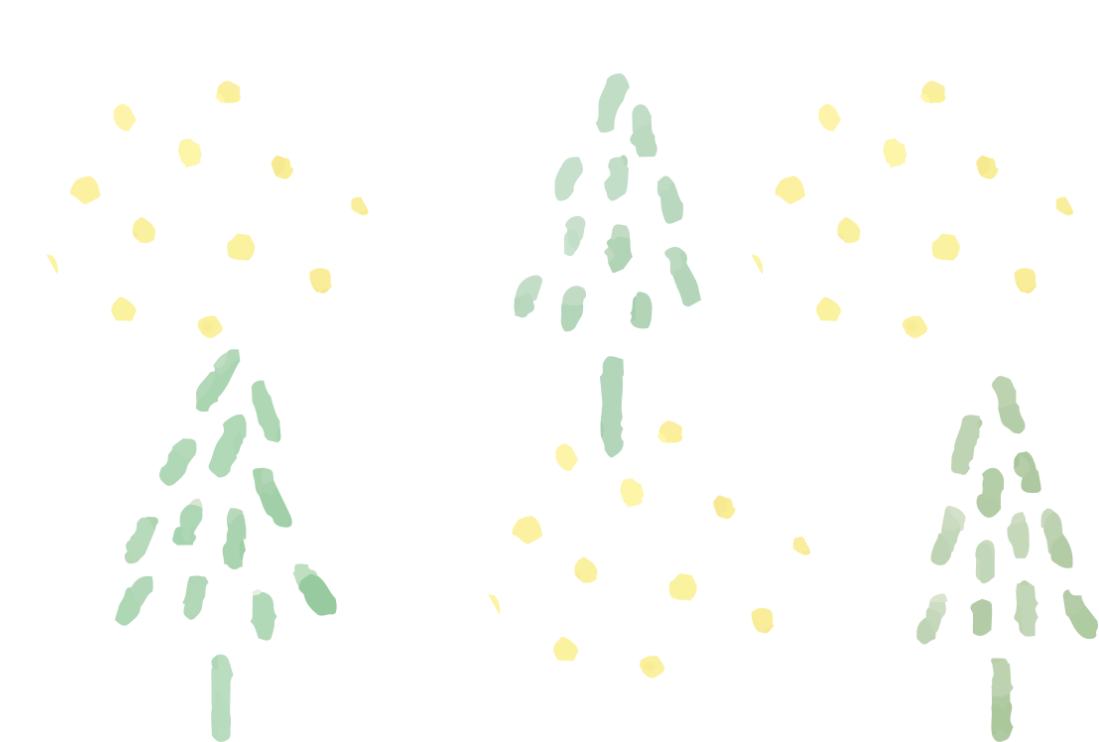お月見

暑かった夏が終わり、朝夕の風はひんやりと、秋の気配が感じられる季節になってきました。夜長に向かうこれからは、空気が澄んで月が明るく見えると言われています。
今年は9月29日が、「中秋の名月」。この日は空を見上げて、月の神秘的な美しさに癒されてみてはいかがでしょうか。
1年中見ることができる月ですが、「月」は秋を意味する季語です。その中でも、旧暦の8月15日、十五夜の月は秋の真ん中に出る満月ということで「中秋の名月」と呼ばれるようになったそうです。
日本には昔から、その夜に浮かぶ月を眺めて収穫に感謝する「お月見」の風習があり、今でも楽しまれています。
「お月見」は、五穀豊穣を願い、秋の実りに感謝する行事なのです。
日本では明治時代に新暦が用いられるようになるまで、月の動きを通して季節の変化を知り、月のリズムに合わせて暮らしを組み立ててきました。
月の満ち欠けを暦として生活してきた昔の人と比べると、現代の私たちは月に感謝することは少なくなったかもしれません。
それでも、絵本に登場する月には目鼻があり「お月さま」と呼ばれ、いつも見守ってくれる存在として描かれています。月の満ち欠けのイラストを用いたカレンダーを使っている人も多くいるのではないかと思います。
月は、地球に生命が誕生する前から空に浮かんでリズムを刻んできました。
月を眺めると、太古からの自然や歴史に思いを馳せることができるでしょう。
日々の生活の中で、意識して月を眺めることはありますか?
空の狭い都市部でも、ビルの谷間やベランダから月の存在を感じることができます。
月という圧倒的な存在に触れると、“自分も自然の一部なんだ” “月が自分を見守ってくれている”と心が癒されることと思います。