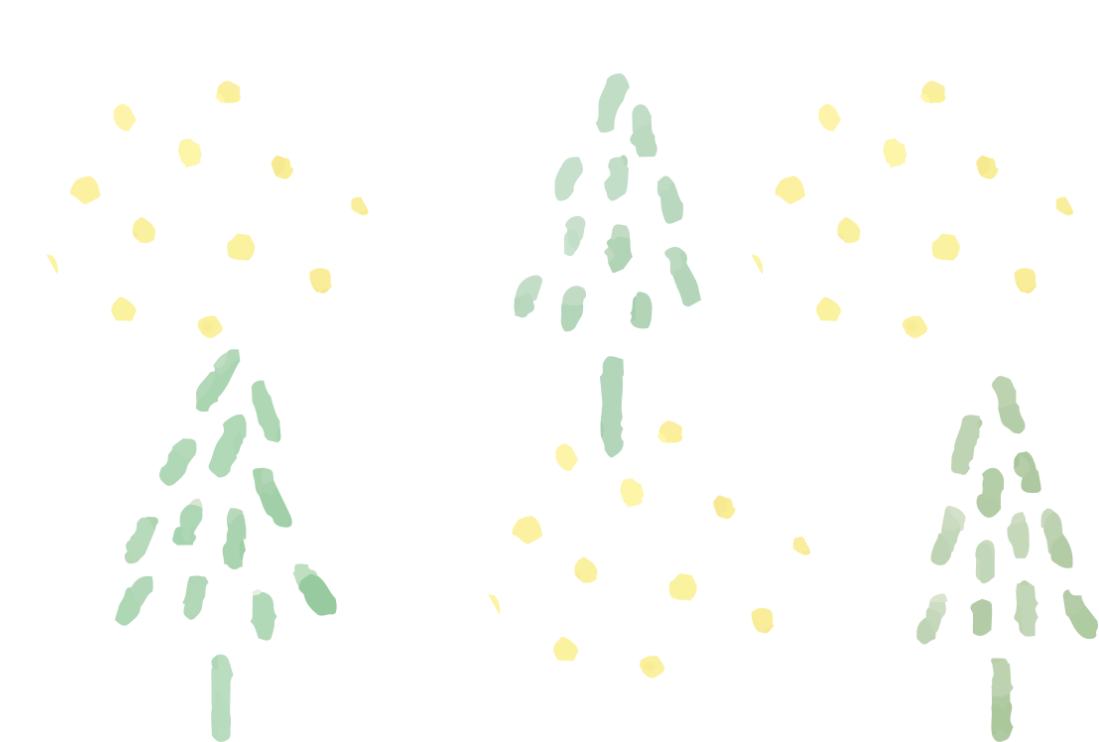大つごもり
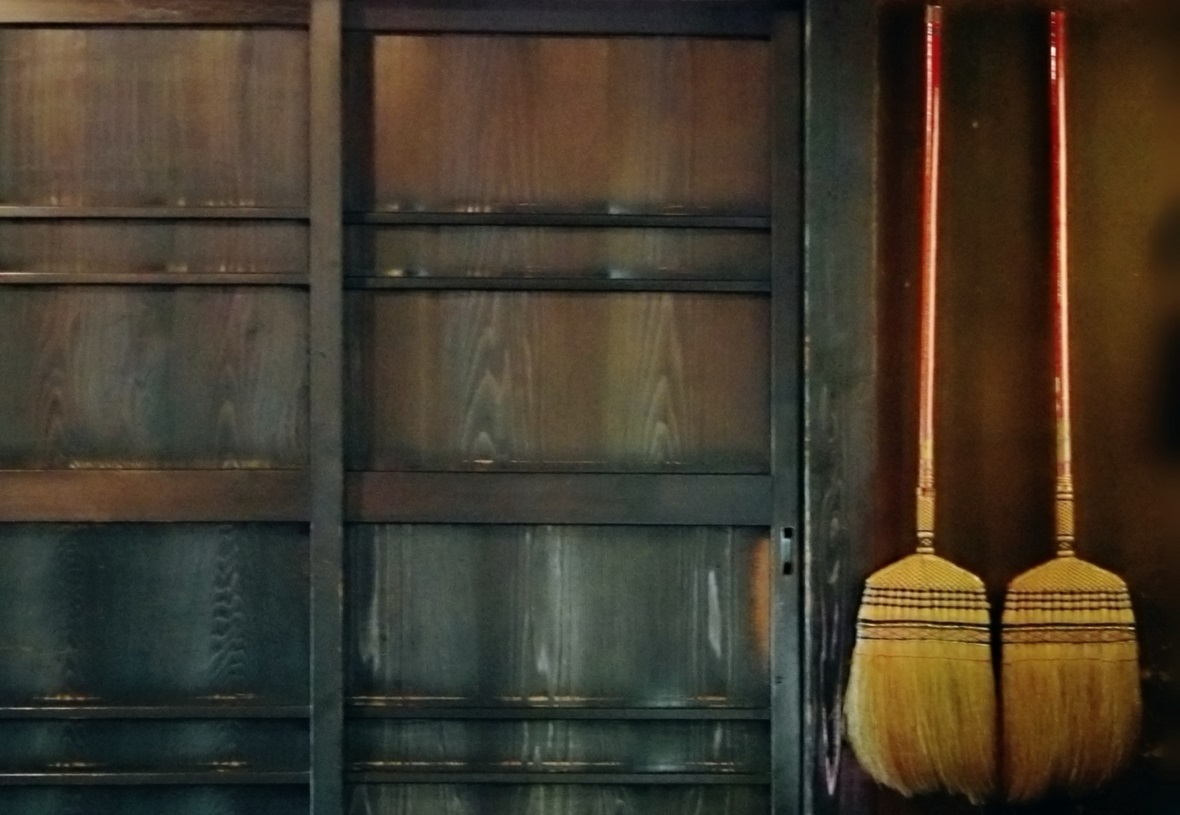
今年も1年の終わりの月を迎えました。12月は「師走」とも呼ばれますが、「師」に限らず、なぜだか慌ただしいような、せわしないような気持ちになってくるのはなぜでしょうか。
その1年の終わりの月の最後の日、12月31日の大晦日は、別名「大つごもり」とも呼ばれます。旧暦では、新月(朔)が毎月の第1日目になっており、毎月の終わりの日は「月が隠れる日=つきごもり」であり、その音が転じて「つごもり」となり、1年の終わりの大晦日は「大つごもり」となったとされます。現在使われている太陽暦は月の満ち欠けのリズムとは異なっているため、大晦日から元日が必ずしも新月と重なっている訳ではありませんが、自然のリズムは私たちの体の中にもあるもののようにも感じられます。
ところで、月にまつわる伝説にもいろいろありますが、その中のひとつに月の宮殿に住む天人の伝説があります。月の宮殿には、白衣の天人が15人、黒衣の天人が15人、総勢30人の天人が住んでいるそうなのですが、15人の当番制で、毎日1人ずつ入れ替わりながら舞を舞うことで月の満ち欠けが起こる…というものです。月で舞っている白衣の天人の人数が増えるごとに月は満ちていき、黒衣の天人の人数が増えるごとに月はだんだん細くなる…。つまり、満月の日は白衣の天人15人が舞っていて、新月の日は黒衣の天人15人が舞っているのだということになります。
新月の夜、月は闇に紛れてしまい、地球上にいる私たちからは見えなくなってしまいますが、そこから無くなってしまった訳ではなく、変わらずにあるのですから、月の天人の伝説はある意味で理にかなっているのかもしれません。そして、見えてはいないけれど、新月の晩でも月の宮殿では黒衣の天人が変わらずに舞っているのだと想像すると、ちょっと励まされるような気持ちにもなります。
古くから、12月13日(地域によっては8日)が「正月事始め」とされ、この日から大晦日、大つごもりに向けて、煤払い、松迎え、餅つきなどの準備を始める日とされているそうです。もともとお正月とは、歳神様をお祀りするための行事であり、年が明けるとともに降臨し、新たな1年の幸せを授けてくれる歳神様をもてなすための準備を半月ほど前から始めるということです。そういったさまざまな準備があるので、12月は忙しく感じられるのかもしれません。
ついつい直前になって「準備ができていない!」と慌ててしまいがちなのですが、古くからある風習や月の天人を見習って、全てその通りにはできないまでも、落ち着いて、穏やかな気持ちで、お正月、歳神様をお迎えできればと思います。